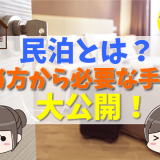- ハウスメーカーに注文住宅を依頼すると4ヵ月~長いと1年ほどかかる
- ハウスメーカーを選ぶ5つのポイント
- 注文住宅のメリット・デメリット、建売住宅との比較
- 検討先を一つの会社に絞る前に、複数の会社から資料や見積もりを収集しておくことがおすすめ
- 〈PR〉「LIFULL HOME’S」さんなどハウスメーカーの比較サービスを利用すれば、限られた予算でも注文住宅が建てられる会社を紹介してくれる!
\条件にマッチした住宅メーカーが見つかる!/

>>>無料カタログをお取り寄せ<<<
注文住宅は自身の理想とする建物を建築することができ、誰しもが憧れる住宅です。しかし、色々と決めないといけない項目が多く、手間と時間がかかるのも事実です。
住宅に対してこだわりたい箇所が多く、手間や時間をかけてもこだわりを実現したい方にとっては、注文住宅が向いているといえます。
多くの相談事や悩み事を解決してきた不動産コンサルタントが、ハウスメーカーの選び方や依頼する流れ、注文住宅の概要やメリット・デメリット、完成するまでの流れについて解説します。
ハウスメーカーに注文住宅を依頼する流れ

ハウスメーカーに注文住宅を依頼してから完成までの流れとして、大まかに以下の6ステップに分けられます。
全体の期間としては早くて4ヶ月、長くて半年~1年ほどかかります。
STEP1 予算と間取りのイメージを決める

注文住宅で家を建てる際にまず決めることは、予算と間取りのイメージです。
予算決めをする際は、ハウスメーカーや金融機関の公式サイトにある住宅ローン返済シミュレーションが参考になります。
間取りのイメージは新居でどのように暮らしたいのかを家族でまず話し合った上で、取り入れたい間取りの優先順位を決め、リストとして書き出すのが大切です。
希望をあらかじめリストとして書き出しておくと複数のハウスメーカーに同じ要望を伝えることができ、それに対するハウスメーカーからの提案を容易に比較検討することができます。
 浜崎編集長
浜崎編集長
 事務員
事務員
STEP2 依頼するハウスメーカーのリストアップと土地探し
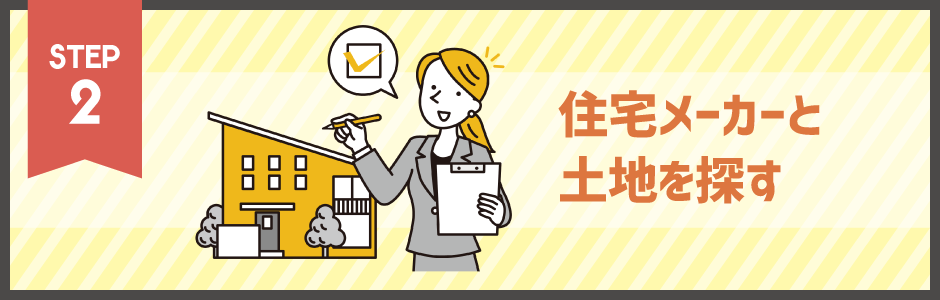
STEP2では、STEP1で決めた間取りのイメージを予算内で実現できるハウスメーカーと土地を探します。
ハウスメーカーの探し方としておすすめなのは、気になるハウスメーカーの住宅展示場を訪れることです。
そこで住宅構造を確認しながら木造にするのか、鉄骨にするかなど担当者に相談してみましょう。 構造以外にも気になることや分からないことなど何でも質問することが大切です。
展示場に訪れた際に「営業マンの対応力や実績」について同時に確認すると相性の判断材料にもなります。
 事務員
事務員
 浜崎編集長
浜崎編集長
STEP3 間取りプランと見積もりの確認

ハウスメーカーをある程度絞ったら、各社に間取りイメージを伝えてプランや見積額を提示してもらいます。
予算額と理想とする家のバランスを考えて、より希望を実現できる業者を選びましょう。
大手のハウスメーカーであれば建築実績が豊富なため大抵の要望に応えられますが、営業担当者の実力に左右されます。
 事務員
事務員
STEP4 住宅ローンの審査と仮契約を結ぶ

STEP3でハウスメーカーに出してもらった見積書の金額を基に、住宅ローン事前審査を受けます。
審査に通り次第、ハウスメーカーと仮契約を結ぶことになります。 住宅ローンの審査が通らないということは家を建てる費用に関して全て自分で用意しなければならないので、家を建てることはほぼ実現不可能になります。
 事務員
事務員
 浜崎編集長
浜崎編集長
STEP5 工事請負契約を結ぶ

間取りと見積もりの詳細が確定したら、ハウスメーカーが住宅建設を行う際に必要な工事請負契約を結んでいよいよ着工準備に入ります。
着工するためには家の構造やプランに問題がないかどうか行政にチェックしてもらう「建築確認申請」をします。
STEP6 住宅ローンの本審査を依頼
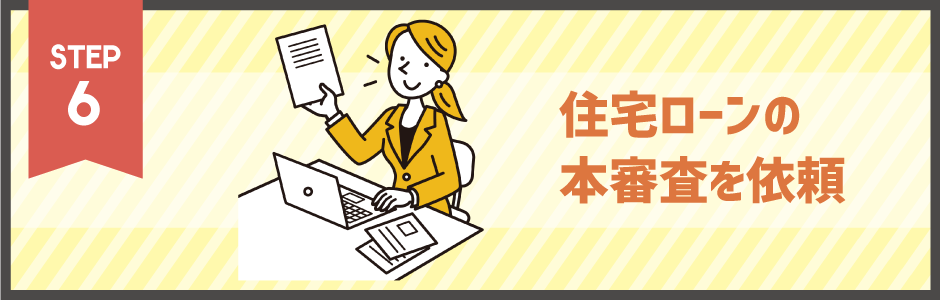
審査に通過したら住宅ローンの本審査を受け、ローン審査に通り次第着工開始です。
 事務員
事務員
 浜崎編集長
浜崎編集長
STEP7 着工
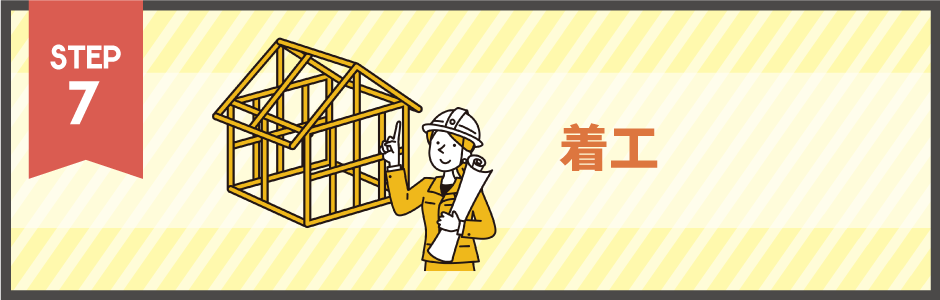
着工してから家が完成するまでの期間はハウスメーカーによって差がありますが、およそ3ヶ月〜6ヶ月です。
STEP8 竣工検査と引き渡し

新居が完成したら、当初の設計書通りに建物が建てられているかどうかを確認する「竣工検査」に依頼主が立ち会います。
また、竣工検査と同時にドアの開け閉めや水回りが適切に流れるかどうかも合わせてチェックします。 竣工検査が何事もなく終了すれば、引き渡し完了となります。
ハウスメーカーの選び方
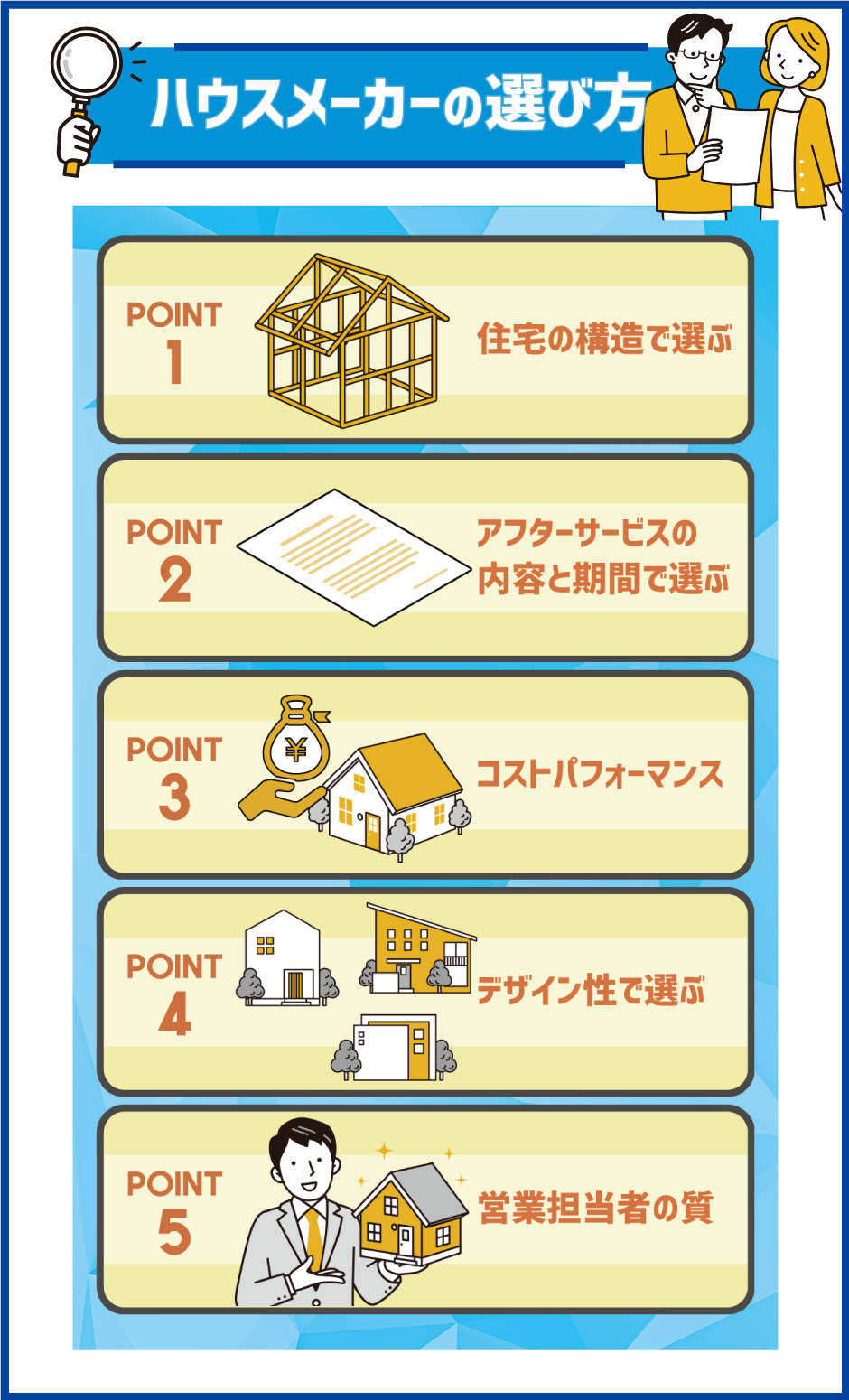
住宅構造(木造・鉄骨)で選ぶ
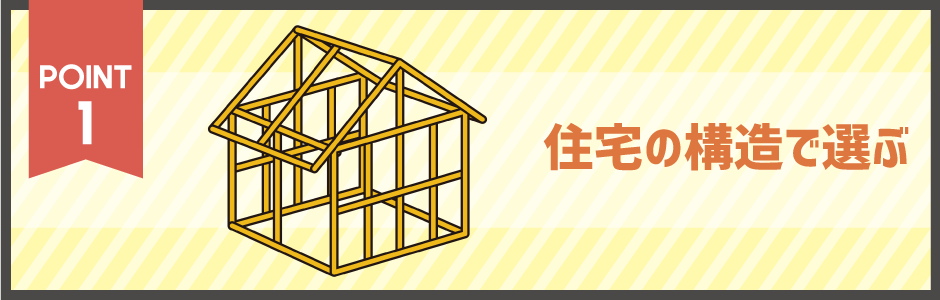
| 木造住宅 | 鉄骨住宅 | |
| メリット | 費用が安い・断熱性が鉄骨住宅よりも高い | 品質が均一化されている |
| デメリット | 耐用年数が鉄骨より短い | 価格は木造より高い |
注文住宅は鉄骨・木造の2種類に大きく分かれます。木造・鉄骨のどちらか片方を取り扱っている業者もいれば、両方の構造を作れる業者もいますので、希望する構造を得意とするハウスメーカーを選んでください。
それぞれのメリット・デメリットを考慮しつつハウスメーカー選びをするのがおすすめです。
アフターサービスの内容と期間で選ぶ
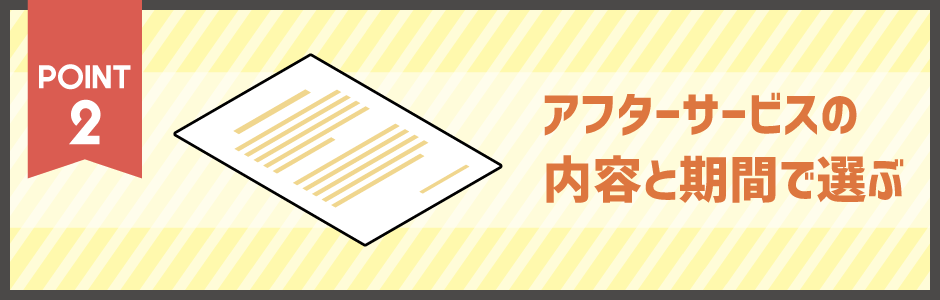
注文住宅は数十年住むので、入居後のアフターサービスの内容は非常に大切です。
ハウスメーカーによって保証内容は違いますが、例えば故障した住宅設備を無料で交換してくれたり、5年おきに無料メンテナンスをしてくれるプランなどがあります。
 事務員
事務員
 浜崎編集長
浜崎編集長
コストパフォーマンス
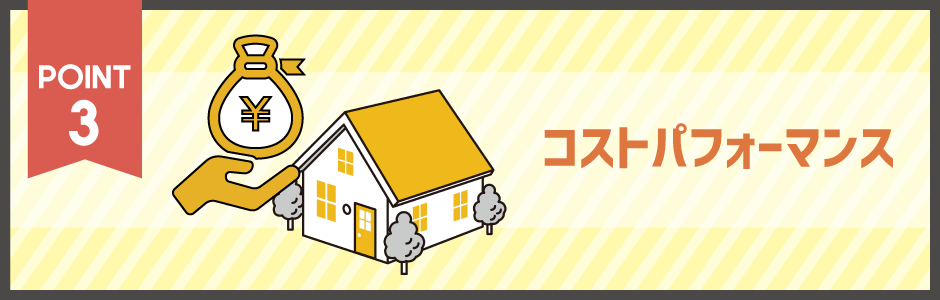
ハウスメーカーの坪単価は、構造にもよりますがかなり幅があります。
全国の平均的な坪単価は70万円~80万円と比較的高めな印象ですが、もちろんハウスメーカーによっては1,000万円台で建築可能なラインナップを用意していたり、中には1,000万円以下のプランを用意しているハウスメーカーも存在します。
しかしながら、1,000万円で建築可能などと謳ってコストパフォーマンスが良さそうに見えるプランでもオプションを付けていくとかなりの金額になってしまったという話はよく耳にします。
また、家の性能面で比較してみると、ローコスト住宅では断熱や耐震・耐火性が乏しかったり、アフターサービスが良くなかったりするケースもあります。
 事務員
事務員
ローコスト住宅と言われる坪単価70万円以下のハウスメーカーから、坪単価80万円以上の高級ハウスメーカーまで選択肢はたくさんありますが、この中から自分たちに一番あった性能やプラン・ハウスメーカーを選ぶことが本当にコストパフォーマンスが高い家づくりにつながります。
デザイン性で選ぶ
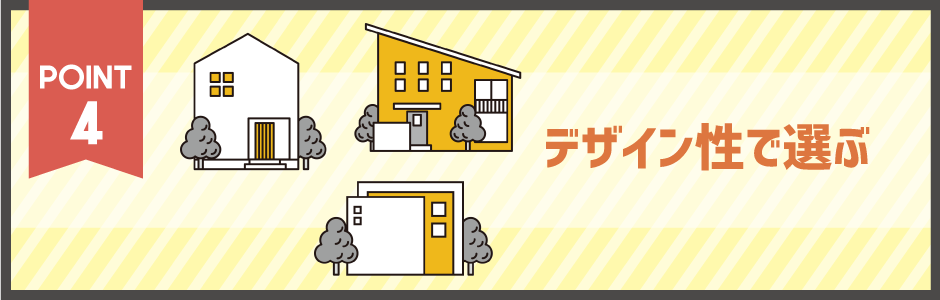
ハウスメーカーによってかなり差がでるのが家のデザインです。ハウスメーカーが用意しているラインナップ毎でも、外観や間取り、使用する木材や建具の色などを変えて様々なニーズに合うような商品を用意しています。
デザインに関しては施主の好みによるので、たくさんのハウスメーカーのホームページやカタログなどで、自分たちが一番好きなものを選ぶのが後悔しないハウスメーカーの選び方につながるでしょう。
営業担当者の質で決める

ハウスメーカーの選び方として最も大切なのは「営業マンが信用できる人間かどうか」です。 条件として最低でもハウスメーカーの営業として3年以上、顧客との商談から住宅の竣工まで全ての工程を一通り理解している営業マンが理想的です。
また、営業マンが顧客が抱える不明点や不安について真摯に向き合ってくれるかどうかも担当者選びの大切なポイントになります。
 事務員
事務員
 浜崎編集長
浜崎編集長
最後に、理想の注文住宅を建てるためのポイントをまとめると以下のようになります。
- 住宅構造(木造or鉄骨)で選ぶ
- アフターサービスの内容と期間で選ぶ
- コストパフォーマンス
- デザイン性で選ぶ
- 営業担当者の質で決める
注文住宅とは

注文住宅とは、所有する土地、もしくはこれから購入する土地に対して自身の建築要望を建築設計事務所やハウスメーカー・工務店などに依頼して自由に設計することのできる住宅です。
フルオーダーとセミオーダーについて
注文住宅には「フルオーダー住宅」と「セミオーダー住宅」とがあります。
フルオーダー住宅
フルオーダー住宅は新築に関する全ての項目について、依頼者が仕様などを選択・指定しながら建築計画を行う住宅です。 指定項目としては以下などです。
- 建築構造・階数・間取り
- 壁・床・天井などの内装材の仕様
- 外壁・屋根などの外装材の仕様
- 使用する木材や断熱材の仕様
- ドア・襖・サッシの仕様
- 水回り設備(台所・浴室・洗面所・トイレ)や家電設備の仕様
自由度は高く完全オリジナルな住宅を建築することができます。しかし相当の建築知識も必要になります。
途中で、一つ一つの建材・設備について、色やグレードなどを選択・決定する必要があるため、時間と手間がかかります。
- 建築計画から建物完成・入居までに時間を要する
- 建材や設備などを個別発注することにより、建築費が高騰
 浜崎編集長
浜崎編集長
セミオーダー住宅
セミオーダー住宅はハウスメーカーや工務店が、あらかじめ基本的な仕様を決めており、依頼者が決められた仕様の中から選択して建築計画を行う住宅です。
セミオーダー住宅は間取り・階数については、依頼者が指定することができ、設備などのグレードも選択することができます。
 浜崎編集長
浜崎編集長
注文住宅と謳っていても一般的にはセミオーダー住宅の場合が多くなります。特にハウスメーカーや工務店に注文住宅を依頼する場合、建築工法や仕様が決まっていることが多く、完全に自由ではありませんので注意が必要です。
- なんの準備も無しに展示場に行くと、そのまま営業に押し切られて契約なんて話も…。
- まずは、気になる資料を一括で請求して比較してみよう!
- ライフルホームなら大手ハウスメーカーから地域密着の工務店まで、幅広い会社の資料が請求できるよ!

- 気になるメーカーが決まったら、あなたの理想の間取りと予算で、ピッタリのプランをメーカーごとに作成!
- 今なら契約・着工でAmazonギフト券をプレゼント!
- たった3分入力で、あなたにとっての理想を見つけて!
注文住宅のメリット

 事務員
事務員
 浜崎編集長
浜崎編集長
- 理想のマイホームを建てることができる
- 家が建てる工程をチェックできる
- 予算の調整がしやすい
理想のマイホームを建てることができる
注文住宅は、これまで実際に見た住宅や、TV・雑誌・カタログなどで見た住宅の気に入った箇所を反映することができ、自身にとって理想のマイホームを建てることができます。
細部まで徹底的にこだわることが、住宅に対する満足度を上げ最大のメリットといえます。
自身のこだわりを存分に反映させたい方にとっては建築設計事務所の設計士に依頼し、フルオーダー住宅を採用する方が良策といえます。
 浜崎編集長
浜崎編集長
家が建てる工程をチェックできる
注文住宅は基礎工事から始まり、建物が徐々に組みあがっていく様子を最初から最後まで見ることができる点がメリットです。
建築主が建築現場に赴き工事作業員の動きを見ているだけでも、建築現場に緊張感が漂い、欠陥工事や手抜き工事の予防に繋がります。
 浜崎編集長
浜崎編集長
予算の調整がしやすい
注文住宅は予算に応じ、調整をし易い点もメリットの一つです。
こだわりたい箇所はグレードを上げ、こだわらなくてもよい箇所はグレードを下げ、コストダウンを図るなどの調整が効きます。
こだわりたい箇所については、あらかじめ優先順位を決めておくことが大切です。
 事務員
事務員
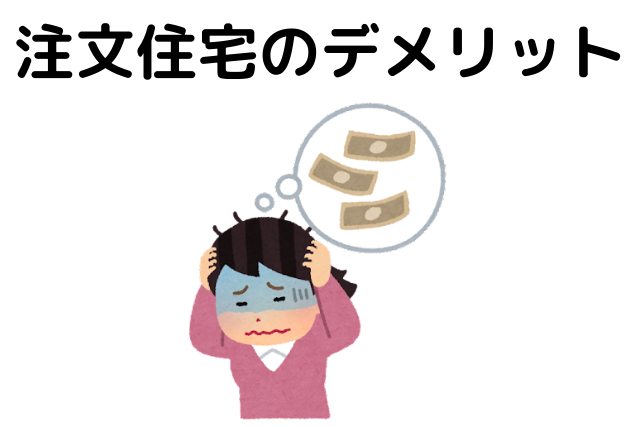
 事務員
事務員
 浜崎編集長
浜崎編集長
- 入居するまでの期間が長い
- 予算オーバーしがち
- 建ててみないと実態がわからない
- 契約から手続き、資金計画など手間がかかる
入居するまでの期間が長い
注文住宅の検討を開始してから入居するまでの期間が1年になることもあります。それだけ時間と手間がかかります。
見積り依頼から設計契約までに1か月~3か月
数社に見積依頼を行い、その中から自身の予算や建築要望(構造・間取り・デザイン・仕様)に沿う業者を吟味・選択します。業者を決定したら、設計契約を交わし詳細設計に入ります。
詳細設計期間:1か月~3か月
詳細部の寸法や仕様などを、打合せしながら決めていきます。詳細設計の期間中、モデルハウスやショールームなどに赴き、カタログなどを参照しながら、外装材・内装材・設備・器具などを決めます。また、それぞれの色合わせを行いながら色を決定します。詳細設計ができましたら建築会社と工事請負契約を交わし、工事に入ります。
工事期間:3か月~6か月
細かな設計変更や仕様変更などを行いながら、工事完成を目指します。住宅が完成しましたら建築主による点検・確認を行い、問題が無ければ入居の運びとなります。以上が概略の工程となりますが、トータルで半年から1年間の期間を要します。
予算オーバーしがち
実現したいアイデアやこだわりポイントが多くなりますと必然的に予算は膨らみ、オーバーしがちとなります。また、建築費以外にも以下などの諸経費がかかります。
- 測量費
- 地盤改良
- 上下水道負担金
- 住宅ローン保証料
- 登記費用・司法書士報酬
- 引っ越し代
その割合は建築費用の3%~7%を占めますので、意外と大きな額になります。こだわりポイントは優先順位を決め、予算と天秤にかけながら実現する必要があります。
建ててみないと実態がわからない
建売住宅は既に建物が完成していますので、実物を見ながら購入することができます。しかし注文住宅は建ててみないと実態がわからないという点がデメリットです。
設計士が作成する平面図や立面図・パースなどを見ながらイメージを膨らませ、ハウスメーカーや工務店などのモデルハウスを見学しながら、建材や設備などを決めていきます。
ただし、モデルハウスの場合、見た目の印象を良くするために、下記のような工夫が行われることもあるので注意してください。
- 部屋の大きさを広めに設計してある
- 建材や設備のグレードを高く設定してある
参考にするのであればハウスメーカーや工務店が客の発注を請けて実際に建築した建物を、引渡し前の内覧会に参加し、見学をさせていただくことです。
 事務員
事務員
契約から手続き、資金計画など手間がかかる
注文住宅は更地から家屋を建てますので家のイメージづくりから始まり、見積り依頼や資金計画、設計契約・工事請負契約などの各種手続きを踏む必要があります。
 事務員
事務員
 浜崎編集長
浜崎編集長
注文住宅と建売住宅は結局どっちがおすすめ?
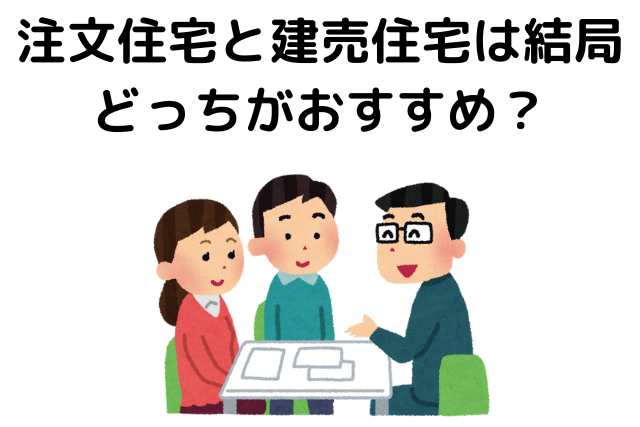
注文住宅にするか、建売住宅にするかの選択は、住宅取得の目的や優先度、予算などによってきまりますので、人それぞれとなります。参考のために、注文住宅と建売住宅の比較表を下記にします。
|
注文住宅(フルオーダー)
|
建売住宅 | |
|
間取りなどの設計自由度
|
非常に高い | ほとんど無い |
|
建材・設備の仕様選択度合
|
幅が広く、こだわりを実現可能 |
幅が狭く、こだわりを出せない
|
|
仕上がりイメージ
|
家屋が完成するまで不明 |
購入する前に、外装・内装などを見学・確認可能
|
| 建築コスト | こだわりを実現させる分、高価 |
注文住宅よりは安価
|
| 資金計画 | 全てをゼロから算出する必要があるため、複雑 |
最初から判明している項目が多いため、容易
|
| 住宅ローン | つなぎ融資などが必要になるため、複雑で割高 |
一つのローンでまとめられるので、容易
|
| 建築工程の確認 | 工事現場へ赴き、現場監督と点検・確認が可能 | 確認できない |
| 入居までの期間 | 検討開始から半年~1年を要す |
いつでも入居可能
|
注文住宅(フルオーダー)ほどには手間や時間をかけたくないけど建売住宅よりはこだわりたい方にとっては、セミオーダー住宅をおすすめします。
まとめ:注文住宅のメリット・デメリットを解説
以上、注文住宅の概要やメリット・デメリット、注文住宅と建売住宅との比較、完成するまでの流れについて解説しました。
注文住宅は自身の理想とするマイホーム建築のため、こだわりたい箇所を実現させることが可能ですが、その分手間と時間と費用がかかります。
そのことを知った上で、それでも一つ一つこだわって建築計画を立案したい方にとっては、注文住宅が向いています。
 事務員
事務員
 浜崎編集長
浜崎編集長
| 関連記事 | |
|---|---|
| 【徹底比較】注文住宅ランキングTOP20 | |
| 評判・口コミ | |
| 飯田産業 | 一条工務店 |
| オープンハウス | スウェーデンハウス |
| 住友林業 | 住友不動産 |
| セキスイハイム | 積水ハウス |
| 大和ハウス | タマホーム |
| トヨタホーム | 日本ハウスHD |
| パナソニックホームズ | 桧家住宅 |
| ヘーベルハウス | ポラテック |
| ミサワホーム | 三井ホーム |
| 三菱地所ホーム | ヤマダホームズ |

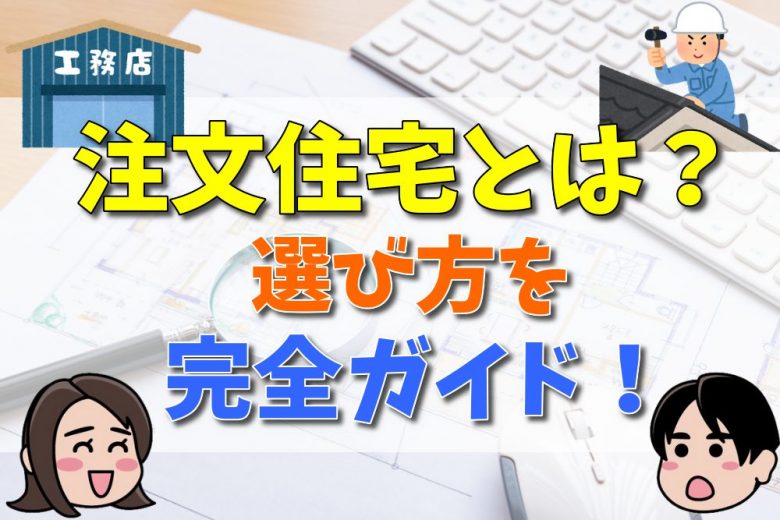
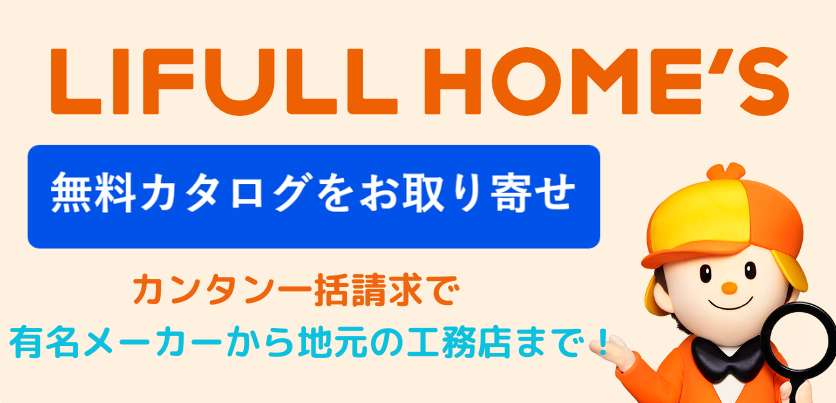
 無料で資料を一括請求する
無料で資料を一括請求する 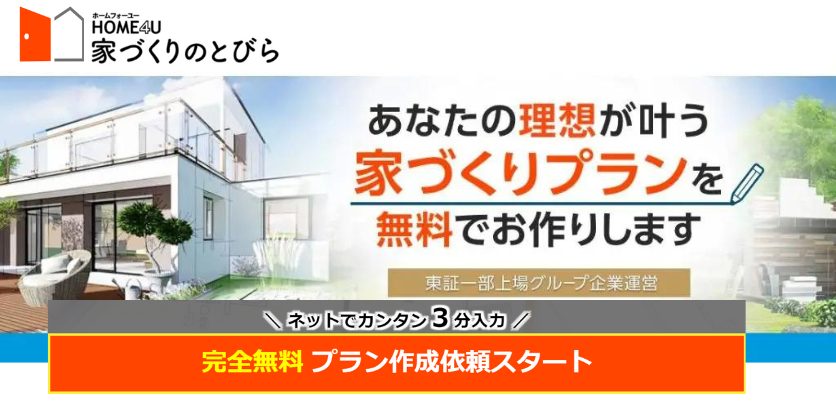
 無料でプランを比較する
無料でプランを比較する