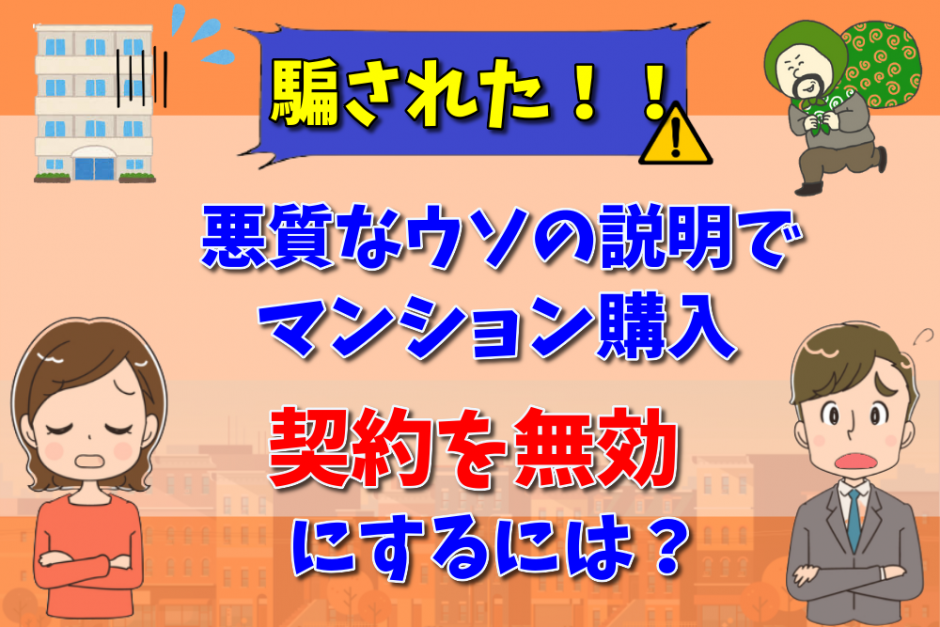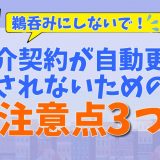- 不動産売買契約は規定に基づいていればキーリングオフできる可能性が高い
- クーリングオフ対象外の場合は消費者契約法で対抗を検討するのが良い
- トラブルが発生したら一刻も早く弁護士に相談することが解決への近道
少子高齢化や人口減少などにより、多くの人が老後の生活資金について不安を感じている今、投資用マンションを購入して資産を増やそうと考える人も増えてきています。
しかし投資ブームに付け込む悪質な業者も少なからず存在するため注意が必要です。
投資にはリスクがつきものですが、せっかくの投資マンションで失敗したくはないですよね。
今回は悪徳業者の虚偽説明に騙されて不利な契約を結ばされた場合の契約解除方法や、クーリングオフについて弁護士が解説します。
不動産をクーリングオフで契約解除するポイント

訪問販売や電話勧誘などで商品やサービスを購入した場合、一定期間内であれば消費者が無条件で契約を解除できる制度「クーリングオフ」はすでに広く知られています。
もちろん不動産売買契約においても条件を満たしていればクーリングオフは利用可能で、違約金や損害賠償金、取引手数料を支払う必要もありません。
宅地建物取引業法第37条の2にある適用規定を具体的に解説します。
業者は「宅地建物取引業者」か
同条文では「宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について」クーリングオフが適用できるとあります。逆に言うと、相手事業者が宅地建物取引業者ではない場合、個人間売買の場合にはクーリングオフを適用できません。契約締結前に必ず確認しておきましょう。
訪問販売や電話勧誘による契約か
条文では「売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした」場合にクーリングオフが適用できるとしています。
この条文はどういう意味ですか?
つまり、訪問販売や電話勧誘を受け、契約のみがクーリングオフの対象となり、消費者が自ら業者の事務所を訪ねたり、消費者側から業者に連絡したことを契機として締結された不動産売買契約はクーリングオフ対象外となります。
クーリングオフの期限内か
訪問販売や電話勧誘販売において事業者は消費者に対し締結した契約はクーリングオフにより無条件で解約できること、および解約期限と解約方法等を説明しなくてはなりません。
消費者は同説明を受けた日を起算日として8日間以内、商品やサービスによっては20日間以内であればクーリングオフを適用できます。
注目すべきポイントは不動産売買契約締結日ではなく、クーリングオフについて説明を受けた日が起算日となることです。
悪質な業者がクーリングオフについて説明を行わなかった場合は、そもそもクーリングオフ期間の開始前となりますから、契約から何年経っていてもクーリングオフが可能です。
クーリングオフに関する書類を受け取っているか、いないか
事業者が消費者に対しクーリングオフについて説明を行う際にはクーリングオフについて記載した書類およびクーリングオフをする場合に必要となる書類を消費者が受け取ることが決められています。
書類を受け取っていないのですが…。
クーリングオフについて口頭で説明を受けたとしても、書類を受け取っていない場合はまだ起算日となっておらず、契約から何年経過していてもクーリングオフが可能です。
クーリングオフ対象外の場合は消費者契約法で対抗を
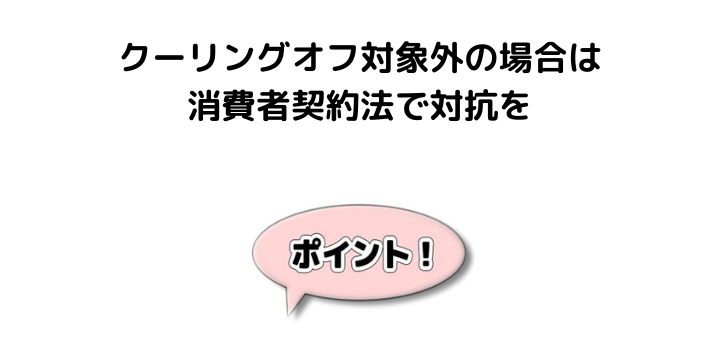
クーリングオフは消費者にとって非常に心強い制度ですが効果が強力なだけに適用条件はかなり厳密なものとなっており、訪問販売や電話勧誘により締結された不動産売買契約以外には適用できません。
では自分から業者に連絡して結んだ契約については泣き寝入りするしかないのでしょうか。このような場合に検討したいのが「消費者契約法」です。
「消費者契約法」とはどんな法律なのか
消費者契約法は消費者(個人)と事業者との間で締結される契約について取り決めた法律です。
消費者と事業者では情報の質、量、交渉力に大きな格差があることから、消費者の保護を図るための特例が定められています。
ただし、消費者契約法は不動産取引を見据えて制定された法律ではないため、投資用マンションを購入契約した自分は消費者にあたるのか、それとも事業者にあたるのかなど、判断に困ることもあるようです。不動産売買トラブルが発生した場合は、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
嘘や不確実な断定に騙された場合は契約を無効にできる
消費者契約法第4条各項では事業者が消費者契約の締結について勧誘をする際に、騙す、誤認させる、困惑させるなどの手段により消費者に契約を承諾させた場合は不動産売買契約をキャンセルできると規定しています。
契約を無効にできれば違約金は支払わなくていいんですか?
はい。同法を根拠として売買契約の解除が認められた場合は、違約金や損害賠償を支払う義務はありません。
事実と異なる、事実と誤認させる説明があった場合
第4条第1項1号では事業者から「重要事項」について不実告知、つまり事実と異なる内容や、事実であるとの誤認を誘導する内容を告げられた場合には、契約の取り消しが可能としています。
重要事項とは消費者が契約を判断する際に影響を与える情報のことです。
例えば5000万円で購入可能と説明を受けていた物件を契約したところ8000万円請求されたとしましょう。これは誰が見ても虚偽の告知であることは明らかですから契約を解除できます。
業者側が騙すつもりはなかったと主張している場合はどうなりますか?
たとえ事業者側に騙す意図がなかったとしても、事実として告げられた内容が客観的に見て明確に違っていれば適用されるため、事業者側の知識不足や思い違いにより不実告知となった場合も、消費者は契約を取り消すことができます。
ただし、この“客観性”がトラブルの種になることもあります。
「静かで快適、日当たり良好」「通勤至便で夜遅くまで営業している店が多く買い物もすぐ行ける」「緑多い環境でのびのび子育て」など、事業者は物件についてさまざまなセールスポイントを強調するものですが、いざ実際に住んでみたら印象が全く違う場合も珍しくありません。
ですが、物件や住環境に対する感じ方は人それぞれのため、説明と事実が明らかに異なることが客観的に認められない場合は、契約取り消しが認められない可能性が高くなります。
第4条第1項2号では将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供した場合は契約の取り消しが可能としています。
「物件周辺の地価は今後絶対に上昇する」「確実に利回り3%以上で運用可能」など、絶対、確実、必ず等の断定フレーズが出てきたら徹底的に疑ってかかるべきです。こうした分かりやすい文言がなかった場合でも、不確実な事項をさも確実であるかのように誤解させる説明を事業者が行った場合には同法が適用されます。
消費者にとっての利益のみ伝え不利益を隠した場合
第4条2項では消費者の利益となる内容だけを告げ、不利益となる事実を故意または重大な過失により告げなかったことにより、消費者が事実を誤認して契約に至った場合には契約の取り消しが可能としています。
事故物件である、隣地にビル建設計画があり近い将来に日照や眺望が遮られる、建物に重大な欠陥がある、係争物件で抵当権が設定されている、等の不告知がこれに当たります。
同項は消費者にとっての利益のみを伝え不利益を伝えなかった場合にのみ適用されます。利益のみ伝えることで優良物件であると誤認させてはならないということです。
また事実不告知が故意または重大な過失により行われた場合のみが適用となります。不利益となる事実を事業者側も知らなかった場合や担当者の知識不足で説明が漏れてしまった場合には適用されません。
事業者が退去指示に応じなかった、消費者の退去を妨害した場合
第4条3項では事業者の不当な行為によって結んだ契約は取り消しが可能としており、8つの行為を不当と規定しています。
なかでも不動産売買取引との関係性が深いと思われる規定は、1.事業者が消費者の自宅や職場で勧誘を行った際、消費者から「帰ってください」「結構です」など事業者に対し退去を要求する意思表示があったにも関わらず退去しなかった場合、2.勧誘現場から消費者が退去したいと意志表示したにも関わらず退去させなかった場合、の2つです。
その場から逃げようとはしたのですが、言葉ではっきりと断ることはできませんでした…。
消費者の意思表示は言葉によるものだけでなく、身振り手振りによる拒否や、その場から逃げようとする行動などによっても成立します。状況によっては監禁罪、不退去罪、強要罪などの刑法に抵触する悪質な不当行為となりますから、断固とした対処が望まれます。
消費者に著しく不利となる契約条項がある場合
消費者契約法第8条と9条では消費者に著しく不利益な契約条項は無効と規定されています。
どのような条項が著しく不利とされるかについては、契約内容によって個別に判断していくことになるため一概には言えません。契約を必ず取り消せるわけではないのですが、消費者契約法第4条の適用が難しい場合は、第8条と第9条が適用できないか確認しましょう。
第8条1項では事業者の損害賠償責任が免除されている契約条項については無効にできると定めています。
例えば「契約書の内容に誤りがあっても修正は一切行わない」「物件に瑕疵が見つかっても契約不適合責任は一切負わない」など本来は事業者が責任を負うべき事項について責任を負わないとしている契約条項は無効となります。
第8条2項では消費者の「解除権」を放棄させる契約条項は無効と定めています。
解除権とは、消費者に対し事業者側が当然負うべき債務を履行しない、物件に隠れた瑕疵があった等、契約内容と著しく異なる状況が認められた場合に、消費者側が契約を解除できる権利です。
第9条では消費者が支払うべき損害賠償金や違約金の規定において、事業者側に法令違反があった場合、条文内で定める基準を超える部分については無効にできると定めています。
例えば消費者の都合で不動産売買契約が解除となった際の違約金規定が一般的な相場を大きく超えていた、消費者が支払う遅延損害金について年14.6%を超える額が設定されていた、などの場合です。
消費者契約法を活用する場合の注意点
消費者は消費者契約法に基づき「取消権」を行使して物件の購入や契約を取り消すことができますが、取消権には時効と期限が設定されています。
契約解除について事業者との交渉が長引き取り消し期限を超えてしまったなどの失敗を防ぐため、話がこじれたら急いで弁護士に相談することをおすすめします。
悪質な虚偽説明によって重要事項を誤認し契約に至った場合、取消権の行使期限は「誤認に気付いたときから6カ月以内」となり、6カ月を超えた場合取消権は消滅します。
事業者の不当行為によって困惑させられ契約した場合についても、「困惑状態から脱した時から数えて6カ月以内」が行使期限となります。また、契約締結から何年も経った後に初めて誤認に気付いた、あるいは困惑から脱出できた場合については、契約締結から5年以内のみ取消権を行使できます。
証拠がないと、どうなりますか?
証拠がないと取消権行使が認められない可能性が高まります。また、契約の取り消し通知は口頭や電話でも可能ですが、これもトラブルの原因となります。必ず書面を作成し内容証明郵便で送付しましょう。
不動産売買契約の解除は期限内に、取り消し根拠を明確に

クーリングオフや消費者契約法の規定に基づいていれば不動産売買契約は解除できる可能性が高いのですが、百戦錬磨の悪質業者であればあるほど契約を取り消されないようあらゆる手段を駆使してきます。
消費者が事業者に対抗するなら客観的で明確な根拠と証拠が必要ですし、たとえ証拠があっても悪質な業者が簡単に応じてくれるとは限りません。トラブルが発生したら一刻も早く弁護士に相談することが解決への近道です。